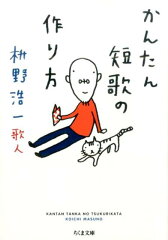短歌に興味を持つタイミングは何度かあった。それを何度も逃してしまった。
最初に短歌に興味を持ったのは、今から10年近く前の頃だった。それから私が短歌を始めるまでに、約5年の月日が必要だった。
当時私は「ダ・ヴィンチ」という雑誌をが好きでよく読んでいて、たまたまそのなかの「短歌ください」というコーナーが目に入った。
このコーナーは今も現役で、毎月テーマが出され、読者が短歌を投稿する。(テーマに囚われない「自由詠」も受け付けている。)
雑誌には、選ばれた短歌と、選者(投稿された短歌を選ぶ人)のコメントが掲載される。
当時は、なんとなく面白いと思う短歌も、よくわからないと思う短歌もあった。でも、短歌と一緒に選者のコメントが入っているので、わからない短歌もそれなりに楽しめた。それから、「ダ・ヴィンチ」を買うたびに「短歌ください」の連載をチェックするようになった。
「短歌ください」の選者は穂村弘(ほむらひろし)さん。当時は選者に注目することもなかったので、それが誰かも考えたことがなく、名前すら見ておらず、語り口から勝手に女性だと思っているくらいだった。
そしてそのときの私はひとつ大きな勘違いをしていた。
「短歌ください」コーナーが特別(自分にとって)面白いだけだろう。
つまり、「短歌全体はきっと面白くない」、と思っていた。
その原因は、おそらく中学〜高校生の頃の国語の授業での苦手意識だったと思う。評論などの点の取りやすい科目よりも曖昧で、歌の内容について先生の説明を聞いて納得しても、「でもこれ、ひとりで読んだら絶対こんな解釈できひんやろ…」と思っていた。
その苦手意識が私の根本にあったため、このときの「短歌ください以外はきっと面白くない」という勘違いが生まれたのだと思う。
そして、「短歌ください」だけを読み続けた私は、さすがに「穂村弘」さんという名前を覚えた。そして、角田光代さんとの共著『異性』を、「なんとなく好きそうだから」という理由で先輩の誕生日にプレゼントしたりもした。
そうして穂村さんの名前を覚えた頃、紀伊国屋書店で開かれていた「ほんのまくら」フェアに行った。このフェアは「本の書き出し」=「本のまくら」だけを手がかりに直感で本を選ぶという内容だった。本にはブックカバーがかけられ、カバーに書き出しの文が印刷されていた。その書き出し以外は何もわからない。

ほんのまくらフェアの様子
私は4冊本を選んだ。

当時選んだ4冊
そのなかに、穂村弘さんの『求愛瞳孔反射』があった。
あした世界が
終わる日に一緒に過ごす人がいない
という書き出しだった。
そして、同じフェアに行った、私が『異性』をプレゼントした先輩は同じく穂村弘さんのエッセイ、『整形前夜』を買っていた。
カップヌードルを食べる時もエレガントに見える人に憧れる。
という書き出しだった。私は詩集でこちらはエッセイだったが、同じフェアで同じ作者の本が当たるなんて奇跡だ、ということで盛り上がった。
そして先に『整形前夜』を読み終わった先輩から、とても面白かったことを告げられた。
そのとき、私は別の友人から「誕生日プレゼントで何か本をあげたい」という話を受け、穂村さんのエッセイを希望し、一緒に行った本屋にあった、穂村さんの最初のエッセイ『世界音痴』を買ってもらった。
『世界音痴』は、「これは自分か?」と思うくらい、激しく共感できる内容だった。自分が子供のころから感じていた、世界への違和感がそこにはあった。それから私は先輩から『整形前夜』も借り、他のエッセイも読み漁った。
最初の勘違いは「「短歌ください」コーナーが特別(自分にとって)面白いだけだろう。」だったが、そこから私は少し進み、
「穂村弘さんだけが、(自分にとって)面白いだけだろう。」に変わった。
短歌への苦手意識はまだあった。そのせいで、エッセイは散々読んだが、歌集には手を出せなかった。理由のひとつは「本気で穂村さんにハマってるのに、穂村さんの本業である歌集が面白くなかったら、失望してしまいそうだから」というものだった。
そして、穂村さんに心酔していた私は、もうひとつ大きな出会いをすることになる。よく行っていた本屋さんで店長と話していて「今、穂村弘さんにハマってるんです」と伝えると、「ウチの常連さんで、『穂村弘さんが好きで短歌もやってる人がボーカルをやってる2人組のミュージシャンのハルカトミユキ』にハマってる人がいる」ことを教えてくれた。
ちょうどその「ハルカトミユキ」がデビューアルバムを出した直後だったので、タワレコですぐに見つけることができた。
穂村さんが好きという情報以外はゼロだったため、まだ好きかどうかはわからないから、そのアルバムではなくインディーズ時代の5曲入りのe.p.『虚言者が夜明けを告げる。僕達が、いつまでも黙っていると思うな。』を買った。
そして1曲目の「Vanilla」ですぐさま心を掴まれた私は、穂村さんと同じく、ハルカトミユキに心酔することになり、CDをすぐに揃え、ネットで読めるインタビューやブログ、Twitterなど、読めるものはすべて読んだ。
そして、ハルカトミユキのボーカルであるハルカさんも、歌集を出していた。私はその歌集を買うまでにも、まだ時間がかかってしまった。
「本気でハルカさんにハマってるのに、歌集が面白くなかったら…」
穂村さんに対して思ったことと同じだった。
だが数ヶ月して、私はハルカさんの歌集、『空中で平泳ぎ』(福島遥名義)を買って読んだ。
名古屋のライブに行った時、持って行った本が面白くなくて、帰りの新幹線で読む本がなくなった私は、グッズ売り場の歌集を手に取った。
どうせ新幹線で暇やし、買ってみようかな…。
というかなり消極的な気持ちだった。でも、あのとき買わなかったら、一生私は歌集を買わなかったんじゃないかという気すらする。
当時、短歌の読み方なんて全然わからない私は、おそるおそるページをめくった。歌詞の世界観とつながる短歌があったり、各章のタイトルがかっこよかったり、言葉の組み合わせが面白かったり、短歌のことがわからなくても面白く、勇気を出して「買って良かった」と思いながら帰宅した。
それでもまだ、
大好きなハルカさんの歌集だから読めただけで、知らない人の歌集は自分には難しいんじゃないか──、と思っていた。
そして、穂村さんの短歌の本を読むことになった。歌集でなく『短歌という爆弾 今すぐ歌人になりたいあなたのために』という、短歌の入門書を買った。
これがとても面白く、最初の数章を読んだ時点で、「めちゃくちゃ面白い」みたいなことをTwitterに書いた。(なぜわざわざ「最初の数章を読んだ時点で、」などと書くかというと、この本は後半急激に難しい内容になるからだ。)
そして、そのツイートを見たフォロワー(かつらいすさん)が「『はじめての短歌』っていう入門書も面白いですよ!」みたいなことを教えてくれた。
そして、続いて読んだ『はじめての短歌』で、私はようやく気づいた。
「短歌ください」だけが面白いんじゃなくて、
穂村弘さんだけが面白いんじゃなくて、
ハルカさんの歌集だからたまたま面白かったんじゃなくて、
「短歌」が面白いんだ──。
そこでようやくそこにたどり着いた。
短歌のことをもっと知りたくなったし、自分でも短歌を詠んでみたくなった。
それからは、短歌に関する面白そうな本をたくさん読んだ。
枡野 浩一さんの『かんたん短歌の作り方』、歌人の俵万智さんが、アーティストの一青窈さんに短歌を教える『短歌の作り方、教えてください』、作家の西 加奈子さんとせきしろさんの「anan」での短歌の連載をまとめた本『ダイオウイカは知らないでしょう』、そして文庫化された『短歌ください』。
短歌の入門書は読み物としても面白い。いろんな人の短歌が読める上に、どこが良いのかも解説でわかる。そして、いろんな歌人の入門書を読むことで、その歌人が大切にしていることも少しわかる気がする。
短歌が単独で載っている歌集という形式ではなく、短歌+文章の構成の本をよく選んでいた。少ししてから、歌集も読むようになった。
いろんな本を読みながら、短歌もどんどん作っていった。
短歌を作り始めてから1ヶ月で歌会も開いた。ペンネームの由来となる『びすこ文庫』という古本屋でいろいろなイベントが行われていたので、そこに「持ち込み企画」として、素人同士で短歌を詠んで、みんなでコメントしあう「短歌ど素人の会」を提案した。
当時はほかの歌会に行くのがこわかったし、どこでそんなイベントをしているのか、その情報の探し方もわからなかった。
「最初から歌会なんて、参加者あつまったの?」と言われることも多いが、初回は10人程度で開催することができた。
まずは一緒に穂村さんにハマっていた先輩、Twitterで『はじめての短歌』をすすめてくれたかつらいすさんなど、身近な人を誘った。
それから、文学バーの読書会に行って『はじめての短歌』を紹介し、プレゼンで注目を集めてからイベントを紹介することで数名集客した。さらに、びすこ文庫の店長さんが、お客さんを2人集めてくれた。
イベントもほとんどやったことのない、短歌のことも知らない素人のしきりだったにも関わらず、非常に楽しく盛り上がり、その帰りの電車で参加者と話しているうちに、短歌以外にも、「やりたいことをどんどんやってみたい」という話になり、その日のうちに「鍋ラボ」を結成した。
2014年の9月だった。
私にとって、短歌のハードルはものすごく高かった。
本当は10年前に「短歌ください」を読み始めた日、短歌を始めたって良かったし、穂村さんにハマってすぐに短歌の本を読んでもよかった。
私はすぐにそれができず、5年もかかってしまった。
それが未だに悔しくて、今もあの頃の自分のために活動を続けている気がする。自分で何か新しいことをやるときの基準のひとつが、「あのときの自分でも興味を持ったか」どうかだ。
短歌に興味がなくても、カードゲームにすればやってくれるんじゃないか。
短歌に興味がなくても、音楽になっていれば聴くんじゃないか。
短歌に興味がなくても、写真と一緒に展示されていたら見るんじゃないか。
短歌に興味がなくても、少しだけ心が動くような方法を探し続けている。
この記事を書いた人

なべとびすこ(鍋ラボ)
TANKANESS編集長兼ライター。短歌カードゲーム「ミソヒトサジ<定食>」「57577 ゴーシチゴーシチシチ(幻冬舎)」、私家版歌集『クランクアップ』発売中。
Twitter @nabelab00
note https://note.mu/nabetobisco
通販 鍋ラボ公式通販
自選短歌
ふるさとと呼ぶには騒がしすぎる町 でもふるさとを他に知らない